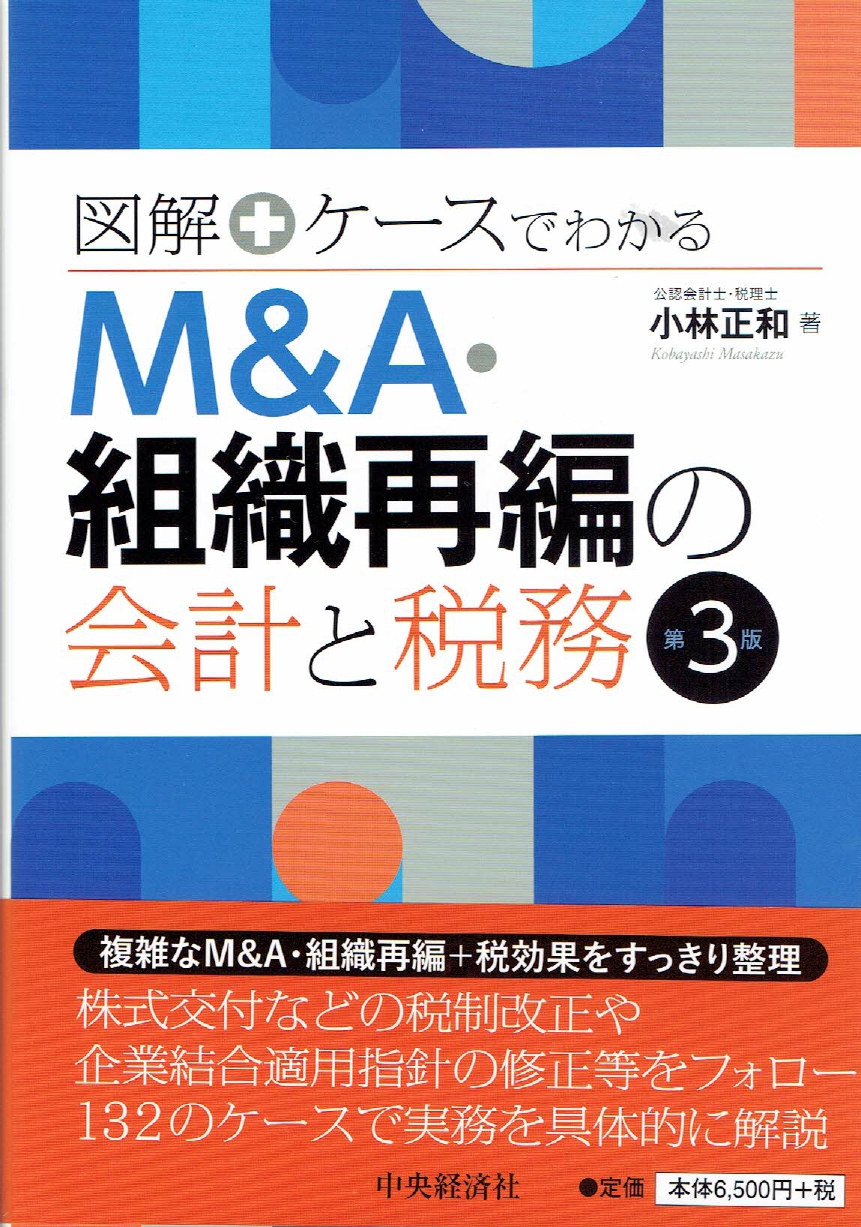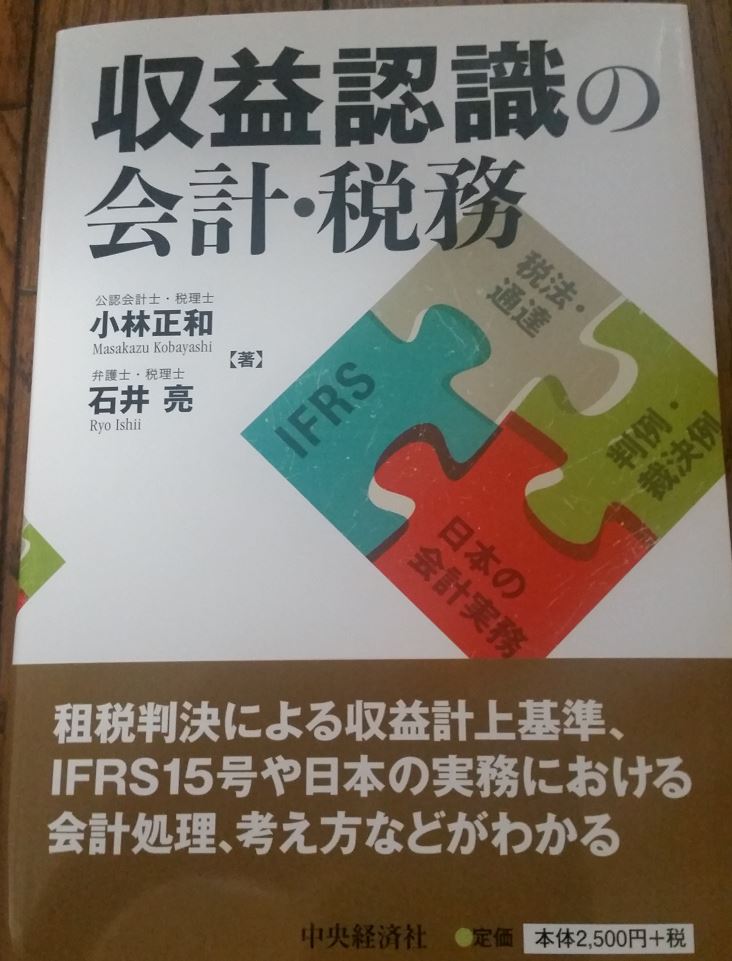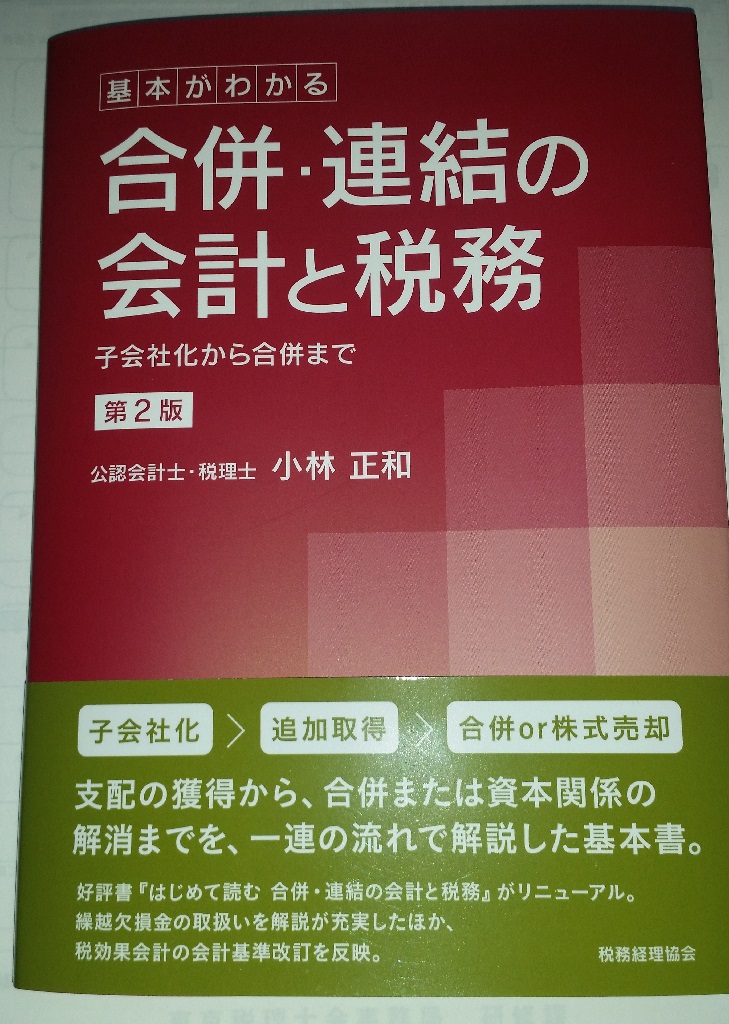会計、税務、監査において、皆さまをサポートします!
小林公認会計士事務所
M&A 固定資産 収益認識 解説CONCEPT
次をクリックしてください
図解+ケースでわかる M&A・組織再編の会計と税務
固定資産・リースの会計と税務
収益認識の会計・税務
基本がわかる 合併・連結の会計と税務
株式追加取得・段階取得の会計と税務
→アマゾンのページへ http://www.amazon.co.jp/dp/450239291X
→ビジネス専門書オンラインへ https://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-39291-7
図解+ケースでわかる M&A・組織再編の会計と税務
は じ め に
筆者は、長年にわたり大手監査法人において会計監査や内部統制の業務を中心に行ってきました。
その中で2007年夏から3年間、企業会計基準委員会において、研究員として企業結合・連結(組織再編、M&A)
に関する会計基準等の開発業務に携わりました。また、昨年には、税理士法人小林会計事務所を設立しております。
2014年7月、「組織再編における株式追加取得・段階取得の会計と税務」(中央経済社)を上梓し、好評を博しておりますが、このたび、
組織再編の様々なケースに対応できるよう、本書を上梓させていただくことができました。
組織再編(M&A)の会計と税務に関しては、企業会計基準委員会や公認会計士協会が公表している会計基準や
適用指針・実務指針により、多くのガイダンスが示されていることに加えて、
法人税法等においても特有の枠組みによる多くの規定があることから、公認会計士や税理士であっても、
あらためて勉強が必要になっています。
さらに、近年、国際会計基準とのコンバージェンスにより、日本の会計基準は、ますます複雑になってきています。
特に、組織再編(M&A)に関する会計基準は2008年に改正され、2013年にもさらなる改正がなされており、
すでに適用が開始されています。
組織再編(M&A)の会計と税務においては、移転する資産や負債を時価評価する場合もあれば、
帳簿価額で会計処理する場合もあります。
いずれの場合でも、支払対価との間で貸借「差額」が生じるので、どう処理するのかもポイントの一つです。
「差額」は、のれん、負ののれん、段階取得損益、資本剰余金などとして計上されるのです。
本書においては、このような複雑な会計と税務の規定、さらには税効果会計について、理解が容易になるように、
経営目的に応じた「他社との組織再編」と「グループ内での組織再編」へ分けるとともに、簡便的なケースを用いてみていきます。
第1部では全体的な概要を確認したうえで、第2部からは、ケースごとにみていきます。第3章は基本編として理解を深めていき、
第4章は応用編として、複雑なケースに税効果会計を適用し、会計処理と税務の扱いをより深くみていきたいと思います。
固定資産・リースの会計と税務
→アマゾンのページへ http://www.amazon.co.jp/dp/4502195014
収益認識の会計・税務
→アマゾンのページへ http://www.amazon.co.jp/dp/4502195014
基本がわかる 合併・連結の会計と税務
は じ め に
組織再編・M&Aの会計と税務に関しては、通常の日常的な会計と税務とは異なる対応が必要となります。
通常の会計や税務に精通している人たちであったとしても、組織再編・M&Aの経験が無いことが多いことから、
改めて勉強する必要があります。
さらに、近年、国際会計基準(IFRS)へのコンバージェンスや、組織再編税制などにより、日本の会計基準と税務は、
ますます複雑になってきています。特に、組織再編(M&A)に関する会計基準は2008年に改正され、
2013年にもさらなる改正がなされ、組織再編税制と異なる規定がなされているため、税効果会計も複雑となっています。
本書においては、このような複雑な会計と税務の規定、さらには税効果会計について、理解が容易になるように、
一連の取引の流れに沿って整理しています。
第1章および第2章では合併と連結の考え方、第3章および第4章では子会社化などの会計処理と税務、
第5章から第7章では子会社化後に合併、売却、追加取得、清算などの会計処理と税務、第8章では税効果会計についてまとめています。
筆者は、長年にわたり大手監査法人において会計監査や内部統制の業務を中心に行ってきました。
その中で2007年夏から3年間、企業会計基準委員会において、研究員として企業結合や連結(組織再編、M&A)
に関する会計基準等の開発業務を経験できました。これらの経験を本書に盛り込めたと考えております。
→ビジネス専門書オンラインへ http://www.biz-book.jp/isbn/978-4-502-10971-3
<組織再編>株式追加取得・段階取得の会計と税務
は じ め に
筆者は、長年にわたり、大手監査法人において会計監査業務、内部統制監査関連業務を中心に行ってきました。
その中で2007年夏から3年間、企業会計基準委員会において、研究員としての業務を経験することができました。
会計監査においては、監査報告書日あるいはレビュー報告書日までに手続きを実施し必ず結論を出さないと
報告書を発行することはできないという厳しい面がありました。
これに比べて、企業会計基準委員会は会議体であり、参加する利害関係者間のコンセンサスを得ることのほうが
重視され、そうしたコンセンサスを得るにはどうすればよいのかといった点に十分配慮する必要があります。
会計監査とはずいぶん異なっていたことが印象的でした。
当時、国際的な会計基準とのコンバージェンスが盛んになされており、筆者は、M&A関連の会計基準等の開発に従事し、
企業結合専門委員会や(連結)特別目的会社専門委員会などの専門委員として、
数多くのプロジェクトに参加する機会を得ることができました。
その後、大手監査法人に戻り、改正された会計基準等が実務でどのように適用され、どのような論点が
議論されているのか、経験することができました。
会計基準等を開発していたときには想定されていなかったようなことが、実務上論点となっていたことには複雑な思いがありました。
本書においては、このような筆者の経験を踏まえて、実務上、論点になりそうな項目における考え方について記述しています。
読者の実務において、その立場に応じて、M&Aに関する会計処理への理解を深めていただきたいと思います。